今日は涼しい一日でしたが、日中はほぼ家の中にいて、「ホームズの世界」の原稿を書いたり、特集記事の修正作業などをしていました。ある本の紹介文を書いていたのですが、もう一度読み始めるとついつい夢中になって読んでしまい、どうやって短文で紹介したものかかなり悩んでしまいました。
さて、情報収集の一環としてSubstackでアカウントを取得して、シャーロック・ホームズ関連のポストを購読しています。
いつも見ているのがPaul Bishopさんのパブリケーション(*)「Sherlcok Adjacent」というもの。

*Substackの仕組みをまだいまいち把握できてないのですが、メール配信もできるし、ブログのように記事もかけるし、動画なども共有できるようです。ある発信者の発信物の総体を何と表現すればよいのかAIに聞いてみたところ「パブリケーション」と言うらしいのですが、若干それでいいのかは疑問もなきにしもあらず。もうすこしSubstack界隈になれていく必要がありそうです。
そんな、Paul Bishopさんの10月4日の最新の配信がタイトルの「Sherlock Holmes in Japan」という記事でした。
ちょうど一昨日のこの日記でBSIの「Japan and Sherlock Holmes」という本のことをちらっと紹介しましたが、その翌日にこのような記事が目に入るというのはシンクロニシティでしょうか。
詳しい内容は上記のページにアクセスいただいて確認いただきたいのですが(Chromeの日本語翻訳機能を使うと楽です)、かなり内容の濃いものとなっていました。
どんな内容か主要なものだけでも以下のようなことに触れられています。
- ホームズが紹介されたのは、日本が明治時代になり西洋文化を積極的に受け入れている流れの中でのことだった。
- ホームズの論理的思考や観察力は、日本の近代化と知的探求の象徴として共感された。初期の翻訳では、理性と教養を備えた理想的な人物として描かれた。
- 日本の文脈でホームズを再解釈した作品として、Dale Furutaniの「The Curious Adventures of Sherlock Holmes in Japan」、Vasudev Murthyの「Sherlock Holmes, The Missing Years: Japan explores a period after Holmes」、Keith E. Webb「Sherlock Holmes in Japan: Nihon No Sharokku Homuzu」などに言及。
- 21世紀にはホームズもさらに大胆に独創的に再解釈され、「Miss. Sherlock」、「憂国のモリアーティ」そして月9ドラマ「シャーロック アントールドストーリーズ」を再創造の最も顕著な例として取り上げている
そして次のようにまとめています。
「シャーロック・ホームズの日本での受容は、文学が国境や時代を超える力を示している。ロンドンに生まれた探偵は、日本の作家によって再解釈され、新たな姿を見せてきた。彼は東西文化、論理と想像力の架け橋となり、創造的対話を通じて物語の可能性を広げた。日本でも、そして他の場所でも、シャーロック・ホームズは時を超えた知性と想像力の旅人として、真実がどこにあろうとも、永遠に探求し続ける。」
明治以降の日本が、西洋からあらゆることを学びながら、それを日本のスタイルに合わせて応用してきたということがホームズにも当てはまるということを指摘しておりなるほどと思わされます。また原題版のシャーロックにも触れつつ、日本化したホームズであっても、知性や真実の探求という普遍性は損なわれていないというのも、私が月9「シャーロック」が好きな理由でもあります。西洋からの学びのあり方を和魂洋才と言っていましたが、ホームズについてもこれがあてはまるのか、逆にホームズの普遍性という魂は失わないところは洋魂和才というべきなのでしょうか。
また、ホームズと日本関連の本も3冊ほど紹介してくれているのも嬉しいところ。私はKeith E. Webbさんの「日本のシャーロック・ホームズ」しか持っていませんので、いずれ他の二冊も入手して読みたいと思います。
また英訳はされていないので触れられていませんが、日本でのホームズの移入史については「日本における シャーロック・ホームズ」によくまとまっています。関心がある方は一読をおすすめします。
移入史を知る決定版だと思いますが、『明治期シャーロック・ホームズ翻訳集成 全3巻』というのもあり、資料としてはこちらもあたるべきだとは思いますが、(お値段のこともあり・・・)未入手なので読めておりません。
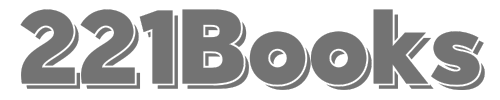

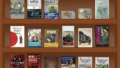

コメント